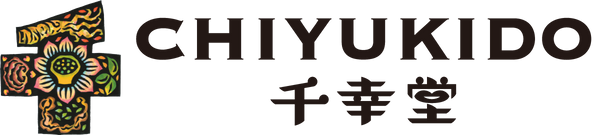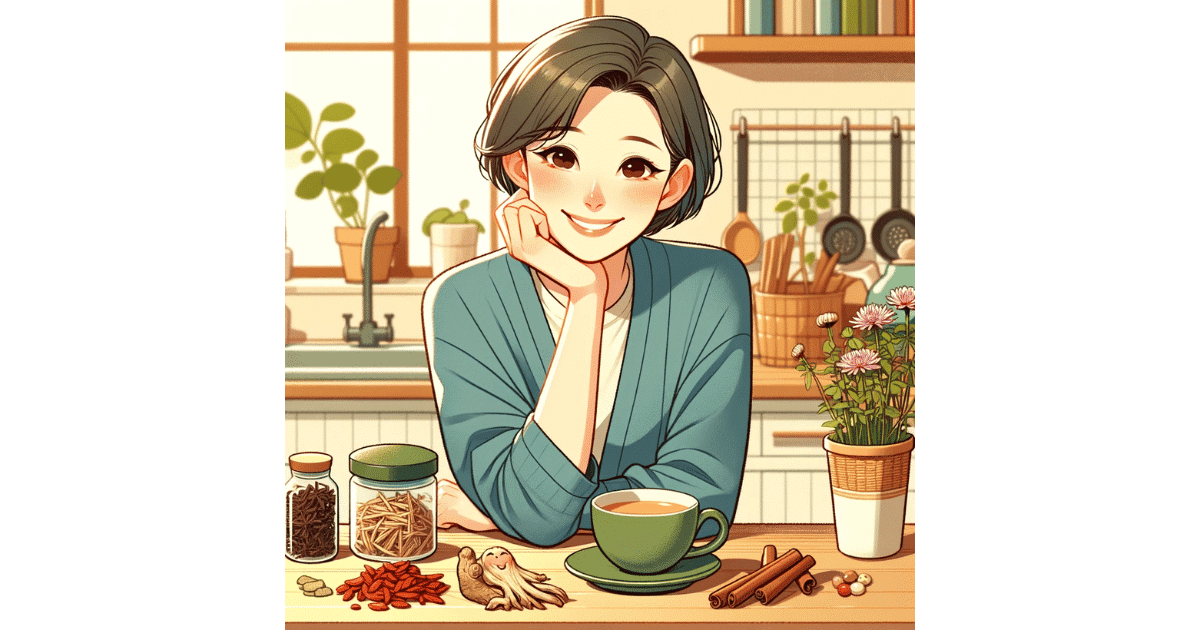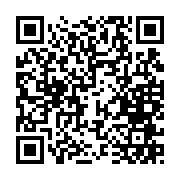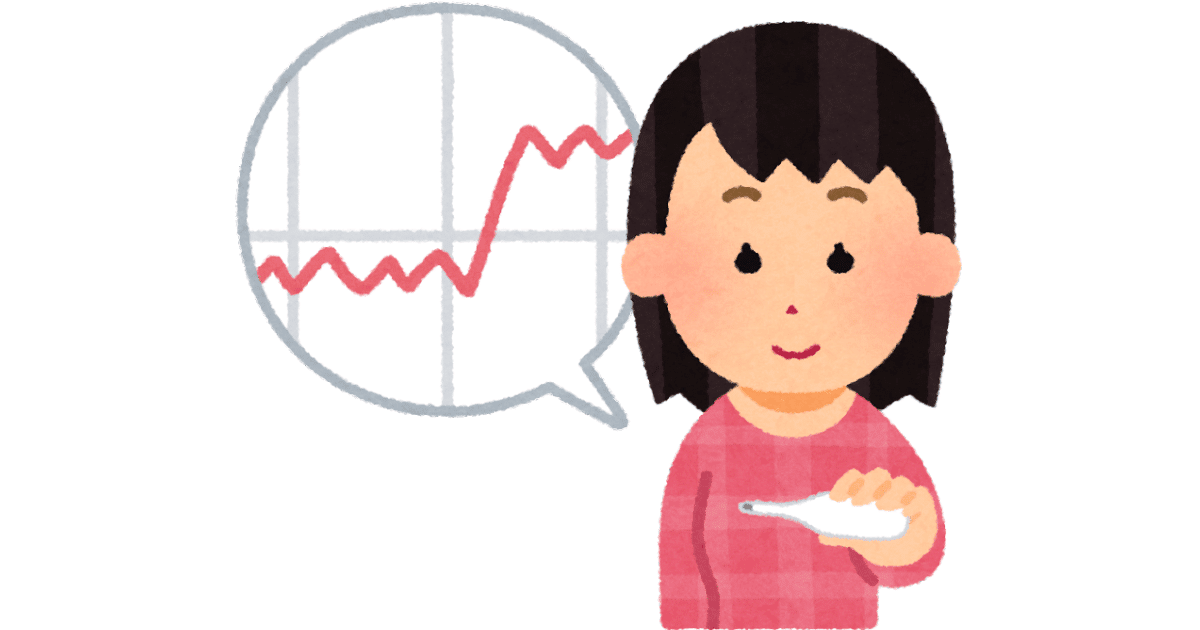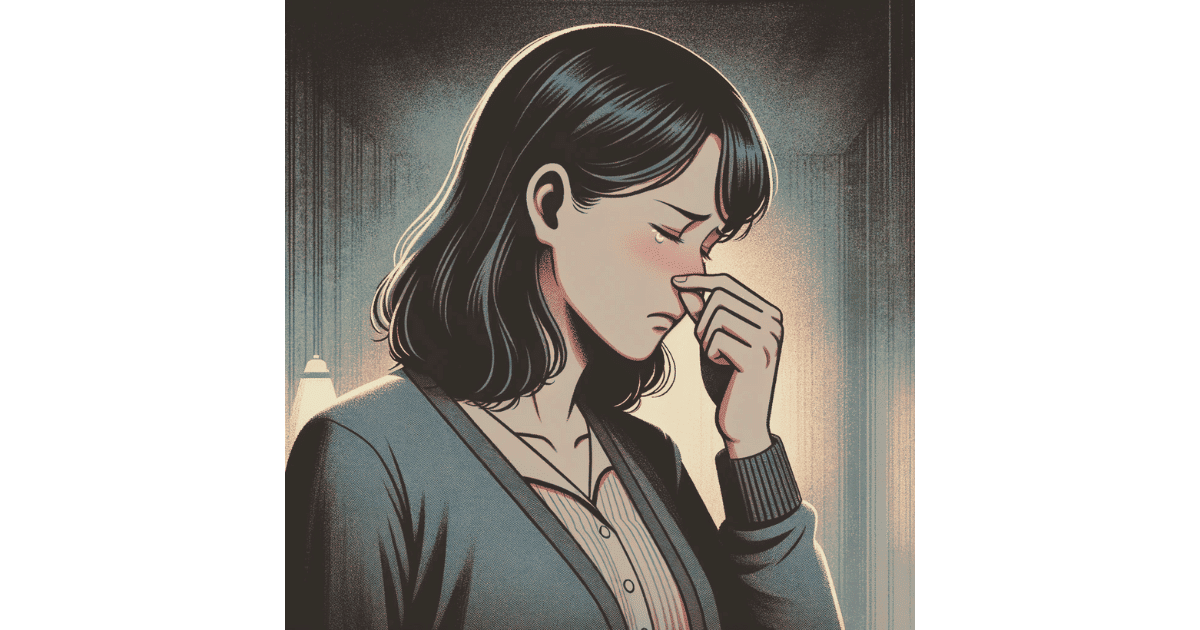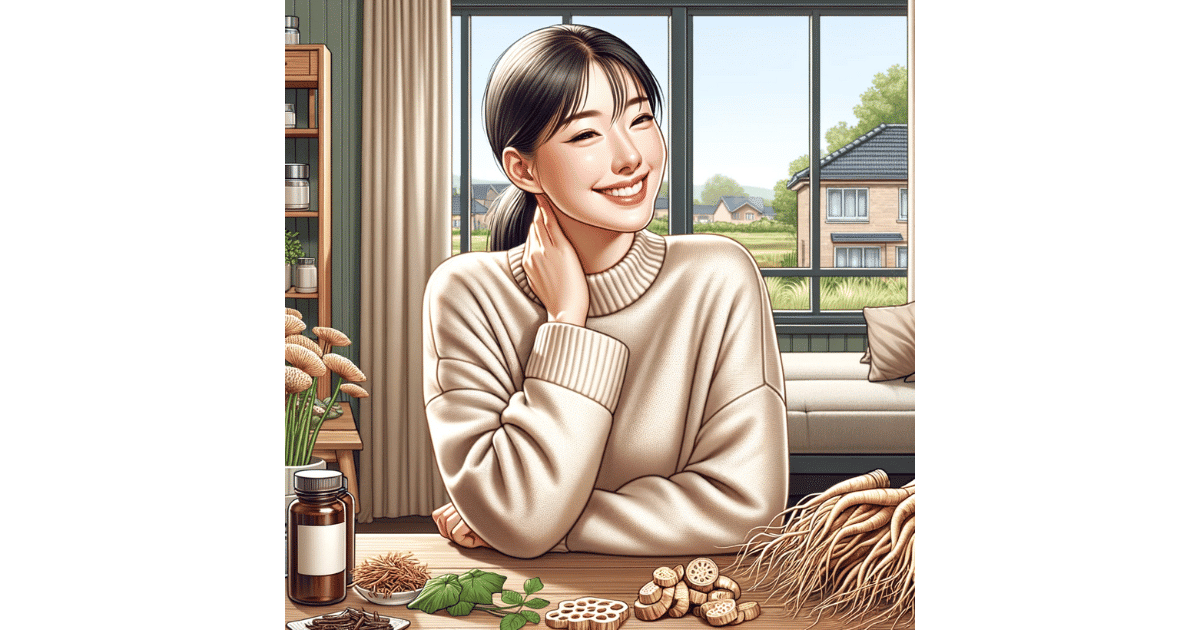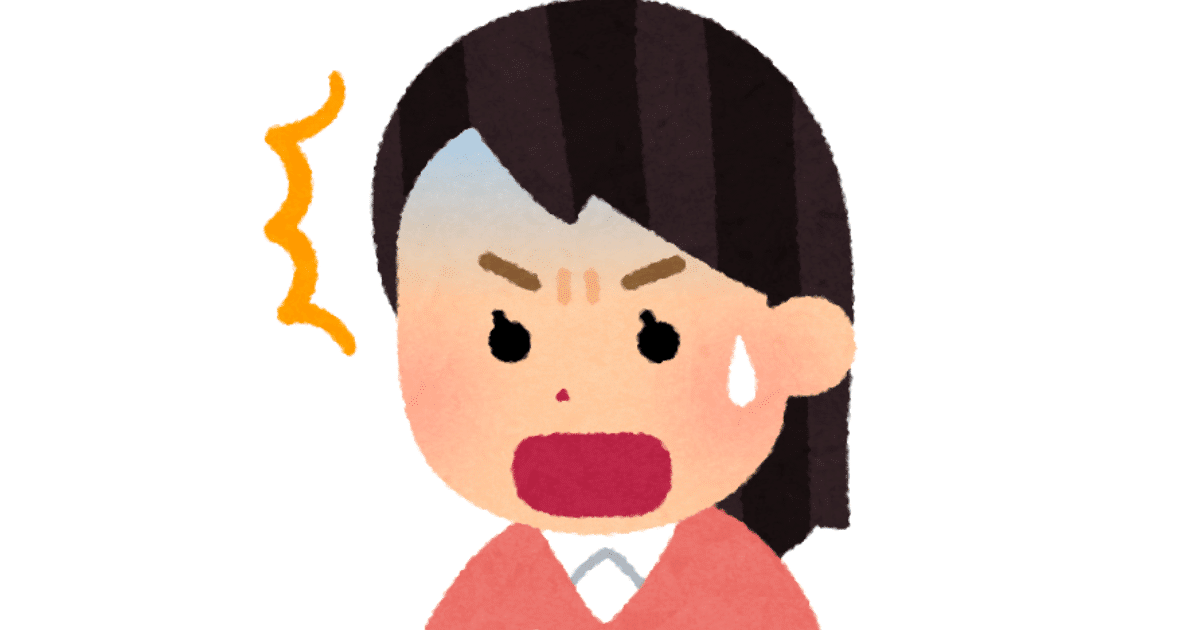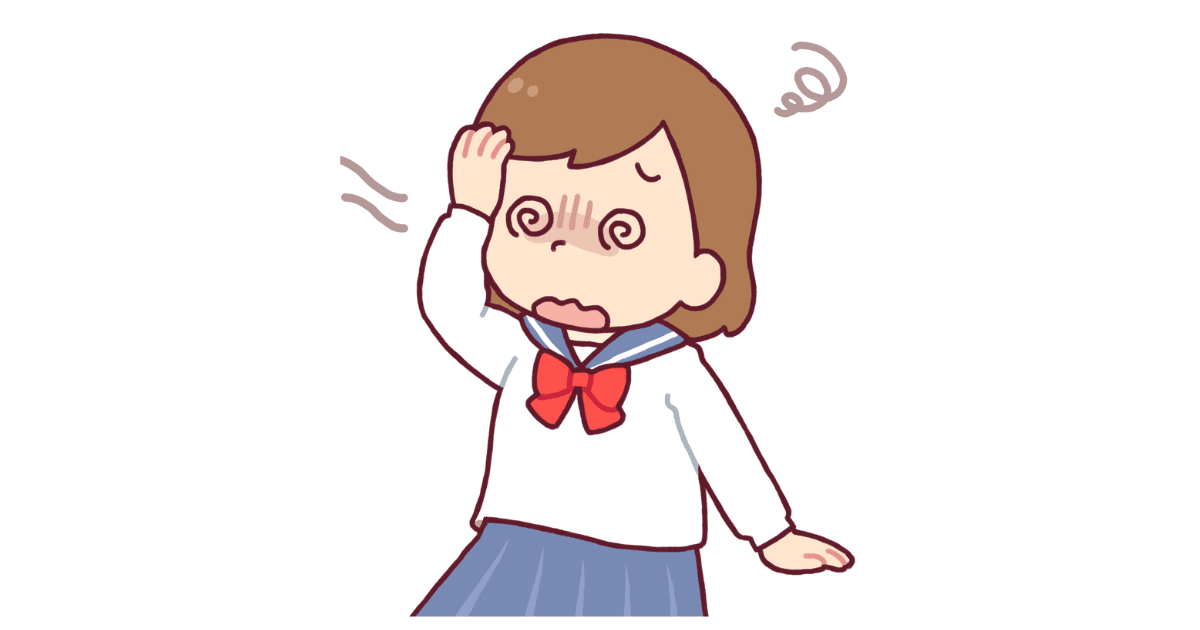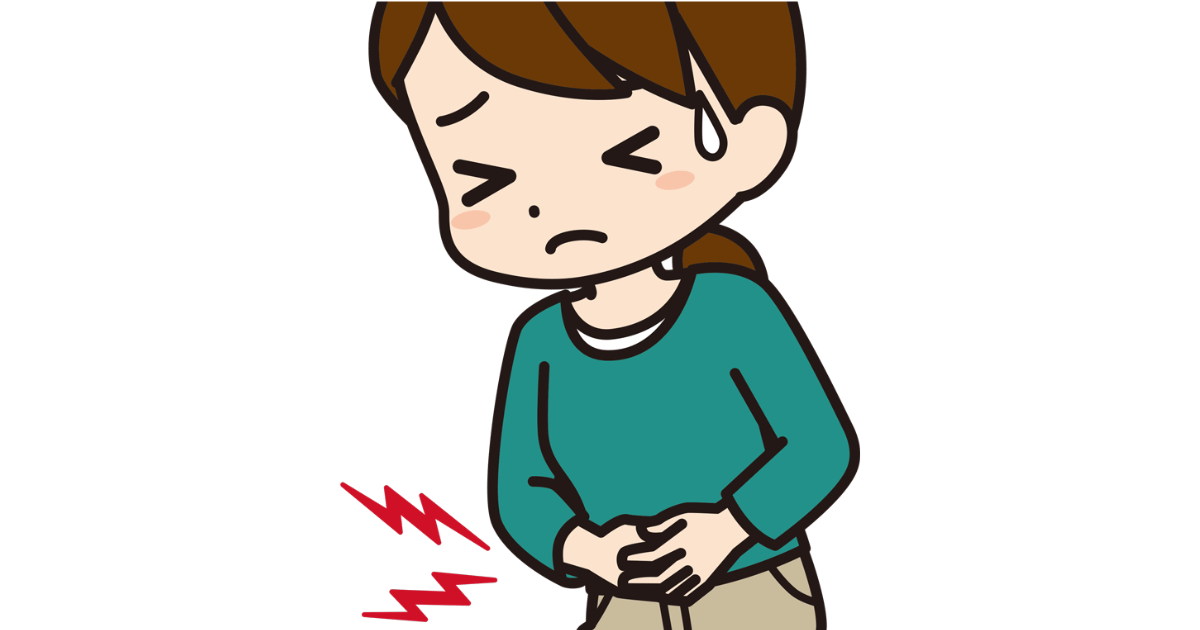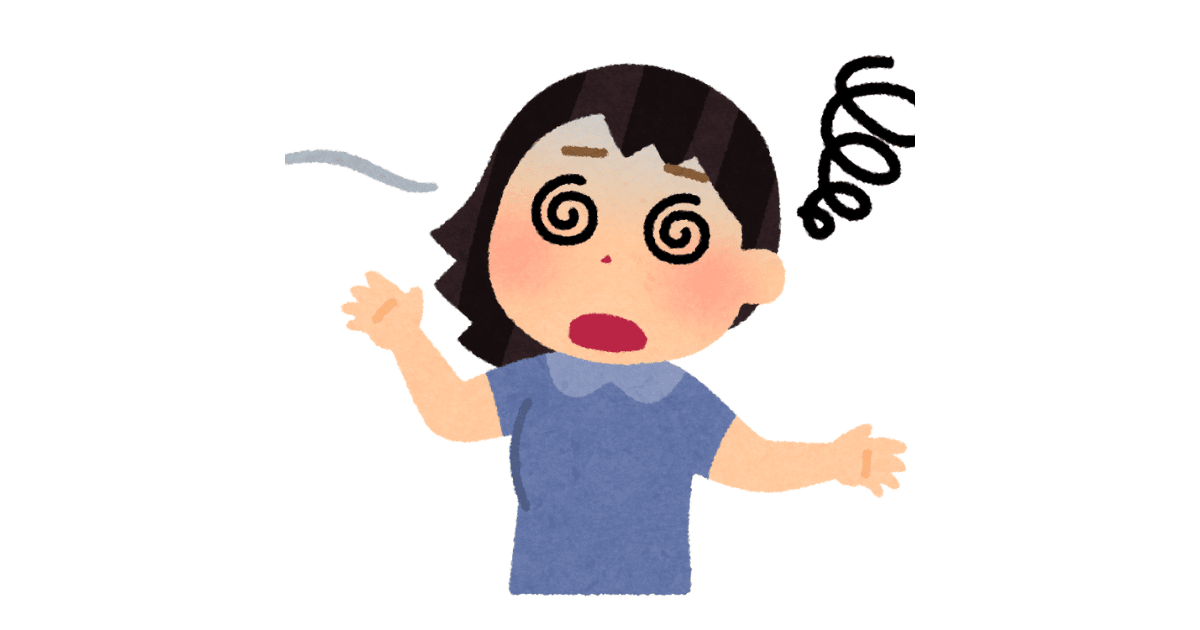母親の介護が続き、仕事も立て込んでいたころ、食事を食べてしばらくしたらげっぷが出始めました。すぐ止まるだろうと思っていましたが、何回も何回も続くので、気持ち悪くなり、こんなことは初めてだったのでネットで調べたら呑気症と書いてありました。心療内科に行くように勧めてあるのですがまずは漢方で何とかなりませんか?(50代女性)
漢方の千幸堂薬局では『呑気症の漢方相談』にメールやLINEで対応しているのでお問い合わせください。

呑気症の症状は、ストレスや精神的なものが非常に関係しているとこれまでの経験から感じています。
しかし、漢方で気の巡りを良くしていくとほとんどが、短期間で改善されます。食事療法とともに漢方薬を服用され1か月でげっぷが出なくなることもあります。またはげっぷがストレスがかかった時だけになり、非常に少なくなったりします。心療内科の薬に抵抗がある方や、病院の薬でも症状が取れない方は、ぜひ、東洋医学の力をお試しください。
呑気症とは?
呑気症(どんきしょう、または空気嚥下症)は、主にストレスや自律神経の乱れが原因で、無意識に空気を飲み込むことでゲップや腹部膨満感などの症状が現れる状態です。漢方では状態は「気滞(きたい)」との関連が深いとされています。気滞は気のエネルギーの流れが滞ってしまう状態を指します。
呑気症に注意したい人
- 不安感や緊張感が強い人
- 日常生活でストレスの負荷が高い人
- 胃腸が弱っている人
なぜ呑気症に漢方が役立つのか?
呑気症の症状と漢方のアプローチ
呑気症は精神的ストレスや自律神経の乱れに起因し、これらの問題が空気の嚥下、いわゆる「げっぷ」を引き起こします。これらの症状に対しては、特にストレスや自律神経の乱れを緩和する漢方薬が役立ちます。
また、吞気症は日常のストレスや疲労により、食欲不振や倦怠感、憂鬱などの症状を引き起こすことが知られています。これらの症状に対しては、胃腸の問題や消化不良に役立つ漢方薬が、呑気症の症状を和らげる助けとなります。
漢方薬は、心の安定とリラックスをサポートし、疲労回復や食欲増進にも効果的であり、呑気症の症状を和らげる働きを助けます。さらに漢方薬は全体のバランスを整えることにより、呑気症の根本的な原因にアプローチし症状の改善を目指します。
漢方による呑気症の予防と日常生活での注意点について
漢方では、吞気症の空気を無意識に飲み込むことで起こるゲップや腹部膨満感といった症状の背後には、「気滞」という状態と関係が深いとされています。そして、この気滞を改善することで症状を緩和できるとされています。また、主な原因は精神的ストレスで、これが血流障害や自律神経の乱れを引き起こし、呑気症を発症させることが知られています。
漢方薬、特に理気薬は、ストレスや自律神経の乱れを和らげ、気の流れを改善する効果があり、症状の改善に寄与します。日常生活でのストレス管理とリラックスを意識した生活、適切な休息が予防に重要であり、そこに漢方薬を用いるのも効果的です。さらに、胃機能の不全も呑気症に関連しているため、胃を温めストレスを減らすのにも漢方薬が役立ちます。
漢方相談から学ぶ:呑気症のケーススタディと漢方と栄養の力
介護や仕事忙しさで呑気症を発症した方の場合は、ストレスからの気滞という症状を楽にする柴胡疎肝湯という漢方と、胃の動きを良くしていく加味平胃散を処方しました。そうすると1週間でげっぷが止まってきました。
しかし、また、ストレスがたまるとげっぷが出そうになるのでそれが怖くて、自宅に漢方を常備しておくようにされました。ストレス対応の栄養素としては、副腎からコルチゾールが出るので、基本となる、スクワレンとビタミンCそして、ミネラルを毎日多めに食べるようにして、ストレスに強い体づくりをされるようになりました。
学校のストレスから呑気症:母親と一緒に取り組まれた漢方と栄養療法
小学校2年生の女の子が呑気症になり、心配で、お母様から連絡ありました。クラスでいじめられているのか?何があるのか不安だといわれていました。ご自分の横で常に「げ、げ、げ」と空気を出している娘を見て、本当にこまっておられました。
小さなお子さんなので、苦い漢方は飲めないので、まずは体力をつける高麗人参と、ストレスに強くなるエゾウコギを混ぜたものを飲んでいただき、最後に、脳の機能を整えるミネラルを食べてもらうようにしたところ、1週間で症状が治まり、学校へ元気に通われるようになりました。
お母さんも夜寝るときには、自律神経を調整する、温灸を耳や胸にしてあげていたそうです。
まだ小さいお子さんに、すぐに心療内科の薬を飲ませるのは、つらいという親御さんも多いと思います。まずは漢方と栄養療法をお試しになってみられても良いかと思います。
漢方相談お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
LINEでもご相談を受け付けております。どうぞお気軽にご利用下さい。